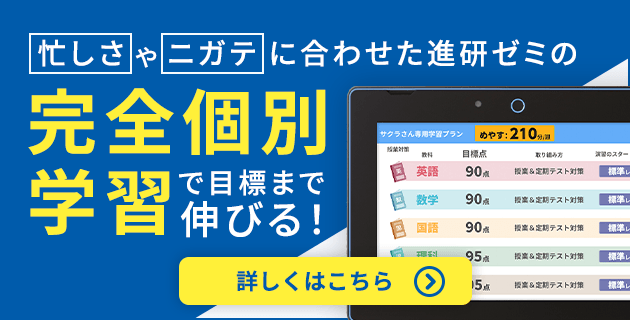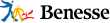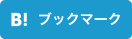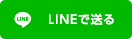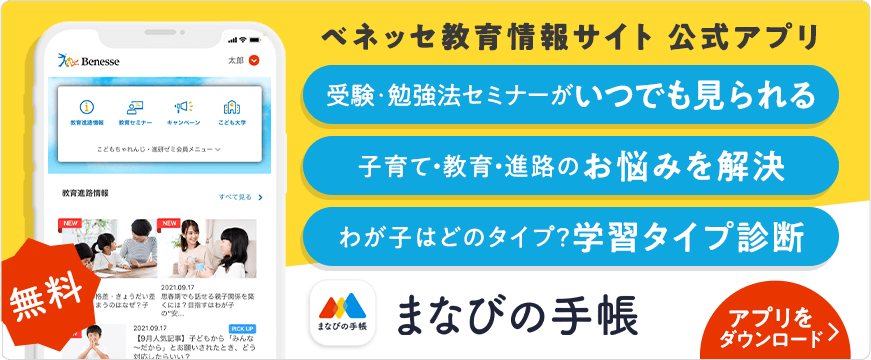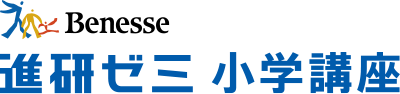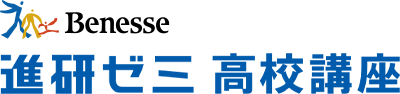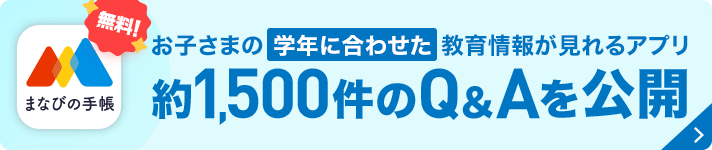高校受験が近づいてくるとよく耳にする「偏差値」。偏差値という言葉を聞いたことがあっても、どんなものなのか説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか? 偏差値はどのように計算すればよいのか、活用する方法はあるのかなど、理解することで自信を持って受験勉強に取り組むことができます。
この記事では、高校受験に欠かせない「偏差値」について、計算方法や特徴、活用方法について見ていきましょう。
偏差値って何?求め方や注意点とは?
偏差値とは、ある集団の中での位置を示す数値のこと。学校や塾で受ける模試などで聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。この偏差値があると、模試を受けた集団の中で自分がどのくらいの位置にいるのかを客観的に知ることができます。たとえば、平均点を取った人の偏差値を50とした場合、平均点より得点が上なら偏差値は55…、60…となり、反対に得点が平均点以下なら45…、40…となります。
偏差値の計算方法
偏差値という言葉を知ってはいるものの、偏差値がどのように計算されているのかを知っている方は少ないのではないでしょうか。偏差値は、以下の計算式で求めることができます。
| 偏差値=(個人の得点-平均点)÷標準偏差×10+50 |
|---|
上記のように、偏差値は個人の成績と集団の平均点とのバランスによって変わります。よって同じ内容の模試で同じ点数を取っても、一緒に模試を受けた集団の平均点が高かったり低かったりすると、偏差値も変化するのです。もちろん、個人の得点と平均点の数値の差が大きければ大きいほど、偏差値も高くなります。
標準偏差の求め方とは?
偏差値を求める計算式に出てきた「標準偏差」。こちらはあまり聞き覚えのない方も多いのではないでしょうか。標準偏差とは、集団の得点の散らばり具合を表す数値のことです。集団にいる個人個人が取った得点のバラつきが大きいほど、標準偏差も高くなります。標準偏差は平均点と同じく、模試や科目によって毎回値が異なるのが特徴です。
それでは、標準偏差が違うことによって、偏差値はどのように変わるのでしょうか。次の例を見てみてください。
【例】Aさんの偏差値(得点60点 平均点50点の場合)
(1) 標準偏差20
(2) 標準偏差10 の場合
(1) (60-50)÷20×10+50=55 ←Aさんの偏差値は55
(2) (60-50)÷10×10+50=60 ←Aさんの偏差値は60
このように、同じ得点・平均点であっても、標準偏差(得点の散らばり)が大きいほど偏差値は低くなります。ただし、平均点ならば標準偏差(得点の散らばり)に関わらず偏差値は50となるので覚えておきましょう。
偏差値を確認する際の注意点
模試を受けたら、偏差値はどのくらいだったのか気になるもの。その偏差値を確認する際に注意したいのが、「母集団が異なると比較ができない」ということ。
たとえば同じ高校の学年内でのテストや、同じレベルの模試受験者間であれば比較できますが、「中学校と高校」「レベルの異なる模試」「受験人数が異なる模試」のような場合は、比較ができなくなります。ですが、問題の難易度や平均点に左右されないため、母集団が安定していれば、客観的な学力の指標になるのです。
たとえば中学校の都道府県単位(数千人)の偏差値と、高校の全国規模(約40万人)で同じ偏差値50だとしても、母集団の人数やレベルが違うため、比較しても意味がありません。また一般的に、志望する高校の偏差値として挙げられている数値は、その模試会社が実施した模試の偏差値です。つまり、すべての模試の偏差値に共通するものではないため、注意しましょう。
偏差値はどのように活用したらいい?
先ほどの計算式で算出した偏差値は、以下のように活用できます。
● 学力の向上・低下の参考にする
● 得意・苦手を把握する
● 高校受験で志望校を決める参考にする
● 志望校の合格ラインまでを確認する
このように、偏差値は高校受験には欠かせません。志望校を決める参考にしたり、志望校の合格ラインを確認するうえでとても重要な役割を果たします。
ただし、模試の種類によって偏差値が変わってくるので注意したいところ。偏差値の数値は母集団(受験者)によって異なるため、「学力が幅広い層の受ける模試」と「学力が高い層に偏った模試」では、偏差値が異なります。偏差値の数値だけに注目するのではなく、志望する高校の偏差値を目安にしながら、自分の実力を上げるための学習が必要です。
偏差値を上げるためにはどうしたらいい?
偏差値を上げるためには、まず「目標点を定めること」が大切です。偏差値を1アップさせるには、「標準偏差+10」が必要な得点といわれています。たとえば、2017年度1年11月記述模試では、偏差値1アップするのに国数英総合で約4.5点、教科別では約1.5〜2.0点ほどが必要という結果に。
これを踏まえると、国数英総合偏差値45の受験生が偏差値50へアップするには、およそ23点(4.5×5=22.5)が必要となります。この得点をそれぞれの教科に振り分けることで、具体的な目標点が定まるのです。
目標点を定めたら、偏差値を上げるために学習にしっかり取り組みましょう。たとえばテスト傾向をもとに学習計画を作成したり、問題演習を通して理解を深めたりするのがおすすめです。
とはいえ、自分に合った学習計画を考えたり、自分のレベルに合った教材を選ぶのはなかなか難しいもの。進研ゼミであれば、目標や志望高校に合わせた「受講コース(レベル)」が選べ、合格へ向けた学習を行うことができます。
『中一講座』・『中二講座』:スタンダード/ハイレベル
『受験準備講座』・『中三受験講座』:受験総合/難関挑戦/最難関挑戦
日々の学習の進路相談のサポートも充実しているため、安心して学習を進めることができます。わからないことがすぐに解消できるだけでなく、やる気をアップするための工夫も盛りだくさんです。
▼進路や学習についてのギモンをチャットボットで解決!|進研ゼミ 中学講座
※お電話での進路相談は会員のかた限定のサービスとなります。
偏差値を上げるには、まずは現在の偏差値を把握することが大事!
偏差値を上げたいのであれば、まずは現在の偏差値を把握することが大切です。進研ゼミ『中学講座』は、レベル別教材や全国規模の<実力診断マークテスト><合格可能性判定模試>などで目標や志望校に合わせて学習を徹底サポートします。とくに受験勉強の始まる中学3年生からは、受験対策教材をお届け。着実に学力を上げて、志望校合格まで導きます。
毎日の学習で疑問が出てきたときも、進研ゼミ中学講座HP内の<ギモン解消ひろば>のFAQで、すぐに解決。 個別に質問もできるので、24時間いつでも学習に関する疑問を解消できます。
さらに、保護者の方向けのサポートとして、最新入試情報や学習の役立ち情報をお届け。学習のコツについて徹底解説します。またお子さまの利用状況を確認できる「取り組みお知らせメール」など、保護者の方にも安心して利用していただけるサポートも充実しているのがポイント。
このように、進研ゼミ『中学講座』は偏差値を上げるための学習のサポートはもちろん、受験に関する不安を取り除くような教材やサポートも充実しています。
▼進路相談などのサポートも充実!進研ゼミ 中学講座の受験対策
偏差値を把握して目標や志望校合格に向けた学習に取り組みましょう
偏差値は、学力が同じでも母集団によって変化するのが特徴です。そのため、偏差値の数値だけに注目するのではなく、志望校の偏差値を目安に、自分の実力を上げていくような学習に取り組むことが大切。偏差値の活用方法として「学力の向上・低下の参考にする」「高校受験で志望校を決める時の参考にする」などが挙げられます。
偏差値を上げたいのであれば、進研ゼミ『中学講座』を活用するのがおすすめ。お子さまに合ったレベル別教材に取り組んで、志望校合格を目指しましょう!
※ここでご紹介している教材・サービスは2023年7月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。