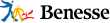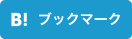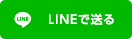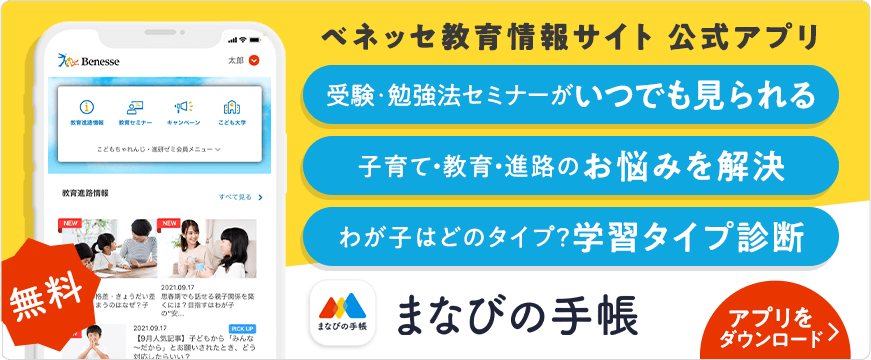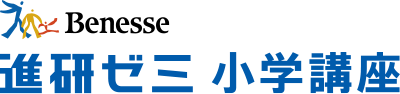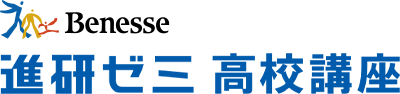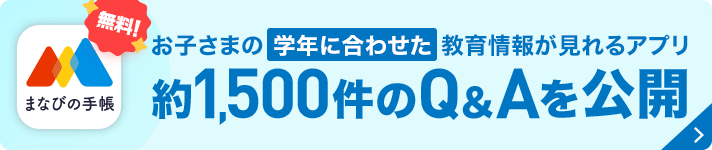2019年に文部科学省が打ち出した「GIGAスクール構想」を皮切りに、昨今の中学校では、タブレットを用いた学習が全国的に広まっています。宿題もタブレットで出題される学校も増えてきているようです。それに伴い、近年は家庭学習においても様々なタブレット学習のサービスが増え、家庭学習を検討中の方にとっては気になるところです。ですが、タブレット学習は今までの学習方法と比較して本当に効率的なのでしょうか?この記事ではタブレット学習のメリット・デメリットやタブレット教育に向いているお子さまの特徴、タブレット教材を選ぶ際のポイントなどをご紹介します。
タブレット学習ってどうなの?メリットとデメリットを紹介
近年多くのタブレット学習のサービスが開発され、ご家庭でのタブレット学習を検討されている方もいるのではないでしょうか。しかし、これまでの紙の教材での学習方法と比較して、タブレット学習が本当に効果的なのか気になりますよね。まず、以下でタブレット学習のメリット・デメリットを見てみましょう
・タブレット学習のメリット
タブレット学習のメリットは、紙の教材より理解がしやすいところです。たとえば理科であれば自然現象の仕組みや実験の流れなど、文字だけでは理解しにくい部分も、映像や画像を使うことで理解しやすくなります。また、英語ならアバターを使ったロールプレイで学習することで、習ったフレーズをどの文脈で使うかといった判断がしやすくなります。音声を繰り返し聞けるので、音と文字が一致しやすくなり、成績も伸びやすくなるのです。
また、一人ひとりのペースや方法に合わせて学習できるため、集団学習のように「わからないまま置いて行かれる」という心配もありません。学習履歴に応じて無駄な部分は省略されるので、今やるべき範囲に集中して取り組め、短時間で効率的に学習できます。なお、勉強自体に苦手意識を持っているお子さまでも、興味を引きだす楽しい演出や工夫があるので、楽しく勉強に取り組めるでしょう。
・タブレット学習のデメリット
タブレット学習の内容は、AIを利用して最適化されることも多くなっていますが、「簡単すぎる」「難しすぎる」などコンテンツのレベルがお子さまに合わないと、せっかくのやる気を低下させてしまうおそれがあります。また、リビングTVを見たり、ベッドでうとうとしたりしながらの「ながら学習」もできてしまうため、結果的に期待した学習効果が得られないことも。また、タブレット教材の購入には特典やキャンペーンが用意されていることもありますが、故障してしまった場合や早期退会した場合、それなりのコストがかかることもあるので注意しましょう。
タブレット教材に向いているお子さまのタイプと、選ぶ際のポイント
タブレット学習には多くのメリットがありますが、お子さまの性格によってはタブレット学習が向いていないこともあります。タブレット学習を導入する際は、お子さまの適性に合わせて検討することが大切です。以下で、タブレット学習に向いているお子さまの特徴を見ていきましょう
こんなお子さまにおすすめ!その①「ニガテ」を残したままにしてしまいがち
苦手な教科や範囲ができると、つい後回しにしたり、その教科だけ勉強しなくなったりしがちです。タブレット学習には楽しく学べる工夫が数多く盛り込まれており、苦手意識を持っている科目でも取り組みやすくなります。また、間違えた問題はただ解説するだけでなく、お子さまの解答に合わせた解説を提示するなど苦手克服の工夫も。解き直しもできるので、苦手をしっかり克服できます。
こんなお子さまにおすすめ!その②難問でつまずいている
小学生と比べて学習の難易度が上がる中学生は、理解が追いつかなかったり難しい問題でつまずいたりしがちです。タブレット教材は動画やアニメーションを活用するため理解しやすく、紙の教材でつまずきがちなお子さまにとっては、わかりやすく感じるかもしれません。お子さまのつまずきポイントに合わせて解説が変わるタブレット教材もあり、次のステップに進む手助けをしてくれるでしょう。
こんなお子さまにおすすめ!その③学習習慣がついていない
机に向かうまでに時間がかかったり、勉強を始めてもすぐ飽きてしまったりと、なかなか家での学習習慣がつかないお子さまもいらっしゃるでしょう。タブレット学習はゲーム感覚で楽しく取り組めるため、お子さまのやる気を引き出しやすいといえるでしょう。興味を引く楽しい演出や適切な目標設定、次の学習への動機付けなど、家庭学習を習慣化する工夫が多数取り入れられています。その日の学習内容を保護者の方に共有する機能もあるため、日々の声かけや励ましもしやすくなるでしょう。
では、実際にタブレット学習を導入する場合、どのような点に気を付けてタブレットを選べばよいのでしょうか。タブレット教材を選ぶ際のポイントを、以下で見ていきましょう。
教材選びのポイントその①受講費は抑えられるのか
お子さま専用のタブレット機器を購入すると、費用がかなりかかる場合があります。入会特典やキャンペーンで費用が抑えられる教材や、タブレットを返却すれば費用がかからない教材など、どのような費用感になっているのか確認しておきましょう。なお、教材によっては特定のコンテンツで学習する場合は追加費用がかかる場合も。基本料金内でどの程度学習できるかも把握しておきましょう。
教材選びのポイントその②タブレット以外の教材はついてくるか
「タブレット学習に慣れると、テストの時に対応しにくいのでは…」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。タブレット学習の中には、タブレット教材のみのものと、タブレット教材に加えて紙の教材や、添削課題がついているものがあります。上記のようなお悩みをお持ちの方は、テスト対策にもなる紙の教材つきのサービスを選ぶとよいでしょう。テストや入試対策になるうえ、デジタル・テキスト両方のメリットを受けられます。「まず学習習慣を付けるためにタブレットのみ」「入試対策のためにテキスト教材も取り入れる」など、お子さまの性格や学習内容に応じて、デジタル教材とテキスト教材を使い分けるとよいでしょう。
デジタルとテキスト(紙教材)のよいところを活かした学習方法で効率よく進められるのは、進研ゼミ『中学講座』!
デジタル教材とテキスト教材、両方のメリットを活かすなら、進研ゼミ『中学講座』がおすすめです。これまでご紹介してきたタブレット学習のメリットに加え、進研ゼミ『中学講座』には以下のような特徴があります。
・お子さまに合わせた個別学習プラン
学習に使える時間や、教科ごとに希望の取り組み方を選択すると、それに合わせて個別の学習プランを提案します。自分で計画を立てる必要がないので、あとはプランに沿って学習を進めるだけ。部活や習い事で忙しい中学生でも、迷わず効率的に学習を進められます。
・習熟スコアで目標までの差を確認
教科ごとに、今の実力と目標をそれぞれスコアで表示します。目標と実力の差がわかるので、どの教科をどれくらい学習すべきかひと目でわかります。また、学習を進めると実力を表す「習熟スコア」が変化。目標スコアとの差が縮まっていく様子がひと目でわかるので、お子さまのやる気が続きます。
・オンラインライブ授業で学習に集中
エキスパート講師のライブ授業が、追加費用なしで受けられます。タブレットはもちろんスマートフォンやPCからも参加でき、録画も残るので忙しいお子さまでも大丈夫。苦手になりやすいポイントを徹底的に解説するので、理解が深まり、やる気が自然に湧いてきます。
・タブレット代が不要なのは、進研ゼミ『中学講座』だけ
主要な通信教育サービスのうち、入会時のタブレット料金が不要なのは、進研ゼミ『中学講座』だけです。入会時のタブレット料金だけで1万円を超えることもあるなか、タブレット料金不要で始められるのは嬉しいですよね。そのほか、オンラインライブ授業や実力診断テスト、英語検定サービスなども追加費用なしで受講でき、追加費用も抑えやすくなっています。
タブレット学習を取り入れながら、進研ゼミ『中学講座』で成績アップを目指しましょう
中学生のお子さまにタブレット学習をお考えの方は、まずタブレット学習のメリット・デメリットを押さえておきましょう。そのうえでタブレット教材の選び方のポイントを把握し、お子さまの性格に合うものを選ぶことが大切です。タブレット教材のなかにはデジタル学習・テキスト学習両方のメリットを兼ね備えたものもあり、特に進研ゼミ『中学講座』はおすすめです。効率よく学習できる進研ゼミ『中学講座』で、お子さまの成績UPを楽しくサポートしてみませんか?
※ここでご紹介している教材・サービスは2023年7月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。